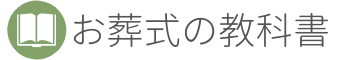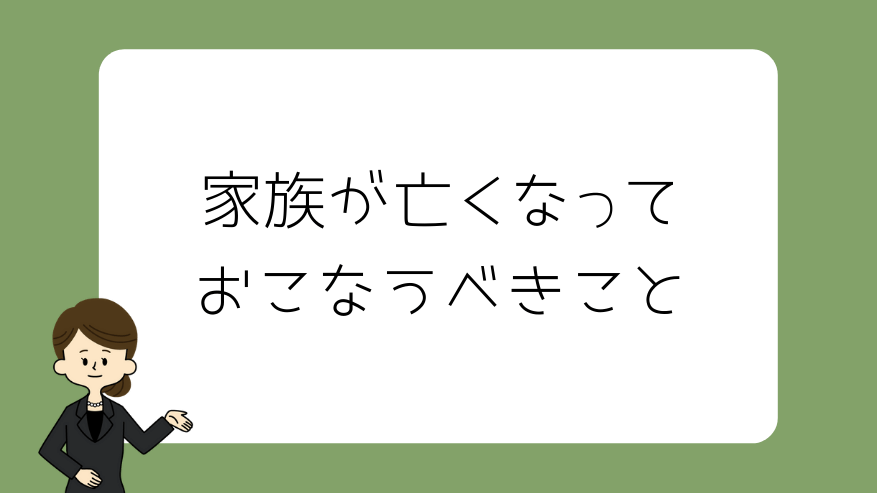ご病気などであなたの家族が亡くなったら、まず何をすればいいのか?
死亡から葬儀完了まで、どのように対応すればいいのか?
この記事では実際に近親者を亡くされた喪主になられる方向けに、要点をおさえた情報を時系列でまとめました。
突然の訃報ではありますが、やるべきことを確実に行わなければ後々困ってしまうような落とし穴もあります。

家族が亡くなってからおこなうべき手順
辛く、打ちひしがれる遺族や近しい方々にとっても酷な事ですが、死後の手続きや葬儀の準備にはやらなければならないことがたくさんあります。

死亡診断書の発行・提出
現代では、比較的病院で最期を迎えられる方が多いようです。
人が亡くなり、医師が死亡を確認すると、「臨終」が告げられます。
自宅で亡くなられた場合はかかりつけ医に連絡し、医師による死亡判定を行ってもらいます。
その後「死亡診断書」が発行されます。
この書類をもとに、7日以内に市区町村役場など自治体に死亡届を提出し、葬儀や火葬の手続きを行います。
医師が立ち会えなかった場合
ケースによっては警察や救急(119番)に連絡する必要があり、すぐには発行されない事もあります
末後の水取り
「末後の水を取る」とは、お別れの儀式のひとつです。
一般的な方法は、箸に脱脂綿を巻いて糸でしばったものに水をふくませ、亡くなった人の口元を軽く湿らせるようにします。
以前は家族が臨終の間際に行なっていましたが、病院で亡くなられた場合は、看護師が準備をしてくれます。
エンゼルケア
「エンゼルケア」とは、逝去後にご遺体を整え、死後少しでもきれいに保つようにする行為を言います。
闘病の末に亡くなられたご遺体を医療器具から解き放つ事も目的であり、看護師が執り行います。
葬儀社や専門業者と提携する病院もあり、費用も様々です。
器具を外し、「清拭」と言ってアルコールでご遺体をきれいにし、鼻や耳に脱脂綿を詰め遺族が用意した衣服に着替えさせ、搬送準備をします。
遺体の搬送
ご自宅に安置する場合、ご遺族が自家用車で搬送するのも法的には問題ありませんが、葬儀社に依頼して専用車で運ぶ事が一般的です。
葬儀社が決まっている場合は一貫して任せられますが、まだ決定していない場合は搬送のみ可能な業者に依頼しましょう。
故人の宗派の確認~葬儀方法と場所、葬儀社の決定
故人の希望などによりあらかじめ葬儀方法が決められていない場合、ご遺族が料金や内容の希望に沿って選ぶことがほとんどでしょう。
以前は宗派の流儀に従いご自宅で通夜を行い、菩提寺のお坊様に供養していただく流れが一般的でした。
しかし最近では、搬送以降の必要手続きを全て葬儀社にお任せする方も増えています。
全てを任せられる安心感はありますが、その分料金も高額になってしまうことが多いので、事前に数社の見積りを取ることをお勧めします。
喪主の決定
葬儀社を決められた場合、葬儀方法もおのずと決まってきます。
葬儀社と親族の打ち合わせの中で、喪主を決定します。
「喪主」とは?
簡単に言えば個人のお別れの儀式全てを執り行う責任者です。
必ずしも一人だけという決まりは無いので、複数で行う事もできます。
多くの場合は個人の配偶者や長男を始め、血縁的に最も近しい人が喪主となります。
とはいえ、最近では性別にこだわらず個人の希望に沿った方が喪主になる事もあります。
喪主は役割も責任も多い大役であり、悲しみや疲れも癒されない状態で全てを一人で管理するのはとても大変です。
他のご家族や親族、地域によってはご近所の方々の協力を得て、無理なく葬儀や手続きを行いましょう。
通夜・葬儀日程を決める
亡くなられてから1,2日のうちに通夜行われ、翌日には告別式という流れがが一般的です。
お寺や葬儀場の都合もありますが、「六曜」と呼ばれる友引、仏滅、などの暦をもとに避けるべき日を考慮して日時を決定します。
菩提寺や参列者への連絡
葬儀の際、仏教であれば菩提寺のお坊様にお経によるご供養をして頂きます。
遠方からの参列者や多忙な現代の事情も考慮し、その後の法要までまとめて済ます事もあります。
いずれにしても、葬儀方法や日程が決まれば、参列いただくためにご連絡する範囲が決まってきます。
亡くなってからかの各種法的手続き
葬儀などの儀式も大切ですが、法律で決められた手続きもたくさんあります。
そのほとんどが亡くなられて速やかに行わなければならないものばかりです。
ご家族で協力し合って、期日内にきちんと手続き出来るようにしましょう。
下記に手続きをまとめました。
亡くなってからすぐにおこなう手続き
| おこなうべきこと | 手続きをおこなう場所 |
| 死亡診断書と死亡届をもらう※1 | 病院の医師が発行 |
| 年金受給停止の手続き | 年金事務所、年金相談センター |
| 埋火葬許可申請※2 | 市役所、火葬場 |
※1 A3用紙1枚に死亡届(左半分)と死亡診断書(右半分)の両方が記載されている
※2 近年では遺族で申請するより葬儀社が代行する場合がほとんど
ポイント
死亡届(死亡診断書)は複数枚コピーを取りましょう
保険金の請求・受け取りの際などに必要となります。
亡くなってから14日以内におこなう手続き
| おこなうべきこと | どこで |
| 年金受給停止の手続き※1 | 年金事務所、年金相談センター |
| 介護保険資格喪失届※2 | 市町村役場 |
| 住民票の抹消届 | 市町村役場 |
| 世帯主の変更届(故人が世帯主であった場合) | 市町村役場 |
※1 厚生年金は会社の担当者にお任せします
※2 故人が65歳以上、要介護認定を受けていた場合
亡くなってから4ヶ月~5年以内におこなう手続き
| おこなうべきこと | いつまで | どこで |
| 所得税準確定申告・納税※1 | 4ヶ月以内 | 管轄税務署 |
| 国民年金の死亡一時金請求 | 2年以内 | 市町村役場
年金事務所 年金相談センター |
| 埋葬料請求※2 | 2年以内 | 加入する健康組合保険 |
| 葬祭費請求※3 | 葬儀から2年以内 | 加入する健康組合保険 |
| 高額医療費の申請※4 | 対象の医療費支払いから2年以内 | 市町村役場の保険年金課 |
| 遺族年金の請求 | 5年以内 | 市町村役場
年金事務所 年金相談センター |
※1 故人が自営業または年収2,000万以上の給与所得者の場合
※2 健康保険加入者の場合
※3 国民健康保険加入者の場合
※4 70歳未満の方で医療費の自己負担額が高額の場合
ポイント
埋葬費と埋葬料は相続財産には含まれません
家族が亡くなってからの手続きまとめ
辛く悲しい別れを惜しむ間もなく、故人のため、家族のためにしなければならない数々の事。
考える時間も少ない中、誰もが後悔のない船出となるよう、準備と手続きをしなければなりません。